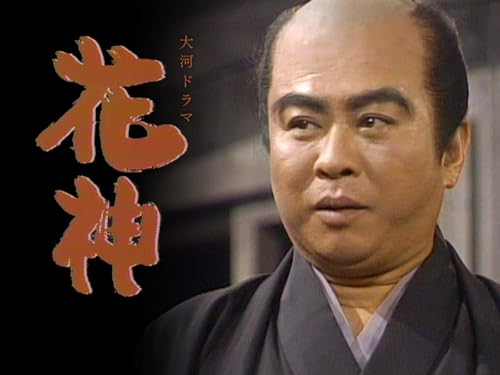歴代の大河ドラマでは、幕末時代を舞台にした作品は数多く制作されてきました。
『花神』(1977年)、『篤姫』(2008年)、『龍馬伝』(2010年)、『八重の桜』(2013年)、『西郷どん』(2018年)、そして『青天を衝け』(2021年)など、人気タイトルは数多いです。
しかし、幕末には西郷隆盛や坂本龍馬といった有名人物だけでなく、まだ大河ドラマの主人公として描かれていない魅力的な人物が数多く存在します。
今回はそんな幕末時代に限定し、大河ドラマの主人公にしてほしい偉人たちをランキング形式で紹介します。
- 大河ドラマと幕末時代の魅力
- 第10位:野村望東尼(のむら・もとに)
- 第9位:河井継之助(かわい・つぎのすけ)
- 第8位:千葉さな子(ちば・さなこ)
- 第7位:鍋島直正(鍋島閑叟)(なべしま・なおまさ/かんそう)
- 第6位:中岡慎太郎(なかおか・しんたろう)
- 第5位:斎藤一(さいとう・はじめ)
- 第4位:松平慶永(春嶽)(まつだいら・よしなが/しゅんがく)
- 第3位:福沢諭吉(ふくざわ・ゆきち)
- 第2位:佐久間象山(さくま・しょうざん)
- 第1位:伊藤博文(いとう・ひろぶみ)
- 番外編:大河ドラマ化は厳しそうだけど見てみたい幕末の偉人たち
- 歴代の幕末大河ドラマを振り返る
- 高視聴率を記録した幕末時代の名場面
- 大河ドラマの主人公によくある質問
- まとめ
大河ドラマと幕末時代の魅力
大河ドラマの中でも幕末時代は、戦国時代と並んで人気の高い時代です。
1963年の大河ドラマ第1作『花の生涯』が井伊直弼を主人公にした幕末物だったことからも、この時代への注目度がうかがえます。
以降も、1968年の『竜馬がゆく』から2021年の『青天を衝け』まで、数多くの幕末大河ドラマが制作されています。
幕末時代が、大河ドラマの題材として人気がある理由はいくつかあります。
まず、激動の時代であること。
ペリー来航から明治維新まで、わずか15年ほどの間に日本は大きく変化しました。
この短期間に凝縮されたドラマが、視聴者を引き付けるのでしょう。
また、多様な立場の人物が多数登場することも魅力です。
倒幕派の志士、佐幕派の武士、開国派と攘夷派、そして時代の変化に翻弄される庶民まで、さまざまな視点から物語を描けます。
さらに、現代に直接つながる時代であることも重要です。
明治維新を経て近代日本が成立したため、現代の私たちとの距離が近く感じられます。
この幕末時代には、大河ドラマの主人公になっていない魅力的な人物が、まだまだいます!
以降では、10位から順番に紹介していきます。
第10位:野村望東尼(のむら・もとに)
第10位は勤王歌人・野村望東尼です。
福岡藩士の夫・野村貞貫の死後、出家して望東尼と号し、和歌をたしなみながら勤王活動を行いました。
- 女性視点から見た維新
- 多くの志士たちを匿った「維新の母」
- 高杉晋作をかくまい、奇兵隊の活動を支えた
- 女性ならではの視点で維新を描ける
- 文化人としての側面
- 和歌を通じた志士たちとの交流
- 当時の文化サロンの中心人物
- 芸術と政治が交錯する時代の証人
- 波乱の人生
- 福岡藩によって姫島に流罪
- 高杉晋作の手引きで救出される
- 高杉晋作の最期を看取る
望東尼を主人公にすることで、維新の英雄たちの「陰の支え」となった人々の物語が描けます。
また、和歌という文化的側面から幕末を捉えられ、これまでとは異なる切り口で時代を表現できるでしょう。
第9位:河井継之助(かわい・つぎのすけ)
第9位は長岡藩家老・河井継之助です。
戊辰戦争で中立を目指しながらも、結果的に新政府軍と戦うことになった悲劇の英雄です。
- 先進的な改革者
- 西洋の軍制改革を実施
- 経済改革で藩財政を立て直す
- ガトリング砲の導入など軍備の近代化
- 中立という理想と現実のジレンマ
- 武装中立を目指した独自の政治思想
- 小千谷談判での悲劇的な決裂
- 理想と現実の狭間で苦悩する姿
- 「河井継之助の敗北」という悲劇性
- 北越戦争での奮戦と最期
- 会津への逃避行での壮絶な死
- 「時代に飲み込まれた英雄」として描ける
河井継之助の物語は、単純な勤王・佐幕の二元論では語れない幕末の複雑さを描き出すのに最適です。
中立という選択肢を模索した彼の姿は、現代にも通じる普遍的なテーマを含んでいます。
第8位:千葉さな子(ちば・さなこ)
第8位は北辰一刀流・千葉道場の娘で、坂本龍馬の婚約者とも言われる千葉さな子です。
その腕前から「剣術小町」と呼ばれた剣の達人でした。
- 女剣士としての異色の存在
- 北辰一刀流の免許皆伝を持つ実力者
- 男装して剣術指南を行った逸話
- 武士の女性の新しい生き方を体現
- 坂本龍馬との恋愛物語
- 「龍馬の許嫁」としての悲恋
- 生涯龍馬を想い続けた純愛
- 維新後も独身を貫いた一途さ
- 維新後の生活
- 学習院女子部の舎監として活躍
- 女子教育に尽力した教育者としての顔
- 時代の変化に適応した柔軟性
千葉さな子を主人公にすれば、坂本龍馬の姿を「千葉さな子」視点で幕末を描けます。
龍馬の物語を別の角度から見直せるうえ、維新後の女性の生き方も含めて描ける人物です。
特に龍馬と別れたのちの半生は、もの悲しい部分もあります……。
第7位:鍋島直正(鍋島閑叟)(なべしま・なおまさ/かんそう)
第7位は佐賀藩主・鍋島直正(閑叟)です。
「幕末の賢侯」の一人として、藩の近代化に成功した佐賀の名君です。
- 科学技術立国の先駆者
- 反射炉の建設で製鉄技術を確立
- アームストロング砲の国産化に成功
- 佐賀藩を「日本の工場」に変貌させた
- 外交センスと政治手腕
- 薩長土肥の一角として活躍
- 新政府での要職を固辞する姿勢
- 実利を重視した現実主義者
- 人材育成の名人
- 大隈重信、江藤新平らを輩出
- 身分にとらわれない能力主義
- 教育投資の重要性を理解
鍋島直正の物語は、技術革新と人材育成という現代にも通じるテーマを描けます。
また、薩長土肥の中で比較的地味な佐賀藩の活躍を知ってもらう良い機会になるでしょう。
第6位:中岡慎太郎(なかおか・しんたろう)
第6位は土佐藩出身の志士・中岡慎太郎です。
坂本龍馬と共に薩長同盟の立役者として活躍しました。
- 陸援隊の創設者
- 海援隊と対をなす組織のリーダー
- 武力討幕路線の推進者
- 実戦指揮官としての能力
- 龍馬との対比で描ける人物像
- 同郷でありながら違う思想を持つ
- 近江屋事件での悲劇的な最期
- 「もう一人の維新の英雄」としての存在
- 思想家としての側面
- 『時勢論』などの著作
- 討幕論の理論的支柱
- 維新後の国家像を構想
中岡慎太郎は龍馬の影に隠れがちですが、実は維新に多大な貢献をした人物です。
龍馬との友情と対立、そして共に散った運命を描くことで、この時代に生き続けることのむずかしさを知れるでしょう。
第5位:斎藤一(さいとう・はじめ)
第5位は新選組三番隊組長・斎藤一です。
維新後は警察官として活躍し、明治の世まで生き抜いた元新選組隊士です。
マンガやアニメの『るろうに剣心』で知っている人も多いでしょう。
- 新選組から警察官への転身
- 会津戦争での奮戦
- 明治警察での活躍
- 時代の変化に適応した生き方
- 剣豪としての生涯
- 新選組随一の剣の使い手
- 無敵の平突きの使い手
- 生涯剣の道を貫いた姿勢
- 長命ゆえの歴史の証人
- 幕末から大正まで生き抜く
- 激動の時代を生き証人として語れる
- 「生き残った者の使命」を描ける
斎藤一の物語は、新選組という敗者側の視点から維新を描きつつ、明治という新時代への適応を描ける貴重な題材です。
一人の剣客の生涯を通じ、時代の変遷を表現できるでしょう。
第4位:松平慶永(春嶽)(まつだいら・よしなが/しゅんがく)
第4位は越前福井藩主・松平慶永(春嶽)です。
「幕末の四賢侯」の筆頭格として、日本の近代化に尽力しました。
- 公武合体から維新への転換
- 政事総裁職として幕政改革に尽力
- 大政奉還への道筋をつける
- 理想と現実の狭間での政治判断
- 人材発掘の天才
- 橋本左内を登用し国事に奔走させる
- 由利公正を見出し、新政府に推薦
- 身分を問わない人材登用の先駆者
- 教育・産業振興の先駆者
- 藩校明道館での先進的教育
- 殖産興業政策の推進
- 近代日本の基礎を築いた改革
松平春嶽の物語は、「上からの改革」の可能性と限界を描くのに最適です。
また、橋本左内との師弟関係や、幕府と新政府の間で苦悩する姿は、ドラマチックな要素に満ちています。
第3位:福沢諭吉(ふくざわ・ゆきち)
第3位は思想家・教育者の福沢諭吉です。
『学問のすゝめ』『文明論之概略』などで知られ、慶應義塾の創設者としても有名です。
以前は1万円札の肖像画で、「諭吉さん」の愛称で親しまれていましたね!
- 知識人としての維新体験
- 咸臨丸での渡米体験
- 文明開化の旗手として活躍
- 西洋文明の紹介者としての役割
- 教育者としての使命
- 慶應義塾の創設と運営
- 「独立自尊」の精神を説く
- 近代日本の人材育成に貢献
- 思想家としての葛藤
- 脱亜論などの著作での議論
- 西洋化と日本の伝統の狭間
- 時代の先を見通す洞察力
福沢諭吉の物語は、武力ではなく知識と教育で日本を変えようとした人物の挑戦を描けます。
幕末から明治にかけての知識人の苦悩と希望を、現代的な視点で捉え直せるでしょう。
第2位:佐久間象山(さくま・しょうざん)
第2位は信州松代藩士・佐久間象山です。
幕末の思想家・科学者として、多くの志士たちに影響を与えました。
- 先見の明を持つ天才
- 西洋砲術・科学技術の研究
- 独自の世界観「東洋道徳、西洋芸術」
- 時代の先を行き過ぎた思想家
- 多彩な弟子たち
- 吉田松陰、坂本龍馬、勝海舟らを指導
- 思想的影響力の大きさ
- 「維新の師」としての存在感
- 悲劇的な最期
- 開国論者として攘夷派に暗殺される
- 時代に理解されなかった天才の宿命
- 京都で散った志の物語
佐久間象山の物語は、幕末の知的水準の高さと、時代の転換期における思想の重要性を描くのに最適です。
彼の教えが維新の志士たちにどう受け継がれていったかを追うことで、幕末維新の本質に迫れるでしょう。
第1位:伊藤博文(いとう・ひろぶみ)
第1位は初代内閣総理大臣・伊藤博文です。
長州藩出身の下級武士から日本の最高指導者へと上り詰めた、立志伝中の人物です。
- 波乱万丈の人生
- 農民から武士へ、そして総理大臣へ
- 英国留学で近代化の必要性を痛感
- 暗殺による悲劇的な最期
- 近代日本の設計者
- 明治憲法の起草
- 内閣制度の創設
- 近代国家システムの構築
- 国際人としての活躍
- 条約改正交渉での奮闘
- 韓国統監としての苦悩
- 東アジア外交の最前線
- 人間的な魅力
- 女性関係などの人間臭さ
- 部下思いのリーダーシップ
- ユーモアセンスと柔軟性
伊藤博文の物語は、幕末から明治、そして日露戦争後までの日本の歩みを一人の人物を通じて描ける壮大なスケールを持っています。
また、彼の人生は「日本の近代化とは何だったのか」という大きなテーマに迫ることができます。
近年の大河ドラマでは渋沢栄一が主人公となりましたが、伊藤博文はまだ単独主人公として描かれていません。
明治維新から150年以上が経過した今こそ、近代日本の礎を築いた彼の功績と苦悩を、大河ドラマとして描く価値があるのではないでしょうか。
番外編:大河ドラマ化は厳しそうだけど見てみたい幕末の偉人たち
ここからは、大河ドラマ化はちょっと難しいけど実現したら面白そうな偉人たちを3人紹介します!
ジョン万次郎(中浜万次郎)
土佐の漁師の子として生まれ、漂流後にアメリカで教育を受けた通訳・教育者です。
日本人として初めてアメリカ本土に上陸した人物でもあります。
- 英語のセリフが多くなり、字幕中心のドラマになりそう
- 当時のアメリカ社会を再現するため、必要な外国人キャストの確保が大変?
- 帰国後の活躍期間が比較的短く、1年間のドラマとして展開するのは厳しいかも……
- 漂流から帰国、そして幕府の通訳として活躍する波乱の人生
- ペリー来航時の通訳として日米交渉の最前線に立つ
- 「世界を見た日本人」の視点から幕末を描ける
物語の半分以上が異国での生活となる可能性があり、従来の大河ドラマとは大きく異なる作品になるかもしれません。
日本人で初めてアメリカ本土の地を踏み、西洋文明を直接体験した彼の物語は、幕末の国際化を象徴する貴重な題材!
ハリー・パークス
幕末から明治にかけての駐日英国公使です。
薩長同盟の裏で暗躍し、日本の近代化に大きな影響を与えました。
- 外国人が主人公はさすがにタブー?
- 米国視点のストーリーは、日本人視聴者の共感を得にくい可能性がある
- 外交の舞台裏という地味なテーマになりがち
- 外国人の視点から見た幕末維新
- 薩長同盟や大政奉還の裏側にある国際関係
- 坂本龍馬や西郷隆盛との交流を新しい視点で描ける
幕末維新の背後で動いていた国際政治の駆け引きを、外交官の視点から描くことで、これまでにない幕末像が見えてくるはずです。
ただし、日本人俳優で外国人を演じるのか、外国人俳優を起用するのか、制作上の課題が多い作品になることは間違いないです。
中野竹子
会津藩の女性武士で、会津戦争で薙刀を振るって戦った娘子隊の隊長です。
22歳の若さで戦死した悲哀の人でもあります……。
- すでに『八重の桜』で会津戦争が詳しく描かれている
- 短い生涯のため、1年間のドラマにするには題材が限られる
- 戦闘シーンが多くなりすぎる可能性
- 薙刀の達人として名高い女性武士の生涯
- 会津戦争を女性武士団の視点から描ける
- 幕末における女性の武士道を描く新しい切り口
女性でありながら武士として最期まで戦い抜いた姿は、幕末の新しい一面を見せてくれるはず。
ただし、会津戦争という限られた時期だけで1年間のドラマを構成するのは、制作上の大きな課題になるでしょう。
歴代の幕末大河ドラマを振り返る
幕末時代を舞台とした大河ドラマは、1963年の第1作『花の生涯』から2021年の『青天を衝け』まで、歴代大河ドラマ約60作品中15作品を数えます。
これらの特徴を時系列順に見ていきましょう。
1960年代の幕末大河ドラマ
『花の生涯』(1963年)
- 初代大河ドラマは幕末の重要人物・井伊直弼が主人公
- 平均視聴率20.2%を記録
- 桜田門外の変という幕末の転換点を描いた作品
『三姉妹』(1967年)
- 架空の旗本家の三姉妹が主人公
- 岡田茉莉子、藤村志保、栗原小巻がトリプル主演
- 平均視聴率19.1%
『竜馬がゆく』(1968年)
- 坂本龍馬の波乱の生涯を描いた作品
- 北大路欣也主演で平均視聴率14.5%
- 白黒時代最後の大河ドラマ
1970年代の幕末大河ドラマ
『勝海舟』(1974年)
- 江戸無血開城の立役者・勝海舟が主人公
- 渡哲也の急病により松方弘樹に主役交代という異例の展開
- 平均視聴率24.2%と当時としては高視聴率を記録
『花神』(1977年)
- 大村益次郎(村田蔵六)の生涯を描く
- 中村梅之助主演で平均視聴率19.0%
- 幕末の群像劇として高杉晋作や吉田松陰も登場
1980年代の幕末大河ドラマ
『獅子の時代』(1980年)
- 架空の会津藩士と薩摩藩士が主人公の異色作
- 菅原文太と加藤剛のW主演
- 平均視聴率21.0%
1990年代の幕末大河ドラマ
『翔ぶが如く』(1990年)
- 西郷隆盛と大久保利通が主人公
- 西田敏行と鹿賀丈史のW主演で平均視聴率23.2%
- 幕末から明治にかけてを描いた二部構成
『徳川慶喜』(1998年)
- 最後の将軍・徳川慶喜が主人公
- 本木雅弘主演で平均視聴率21.1%
- 司馬遼太郎原作で維新の激動を描く
2000年代の幕末大河ドラマ
『新選組!』(2004年)
- 近藤勇を中心とした新選組の物語
- 香取慎吾主演で平均視聴率17.4%
- 三谷幸喜脚本による青春群像劇
『篤姫』(2008年)
- 宮﨑あおい主演で天璋院篤姫の生涯を描く
- 平均視聴率24.5%は幕末大河最高記録
- 女性の視点から見た幕末維新
2010年代以降の幕末大河ドラマ
『龍馬伝』(2010年)
- 福山雅治主演の坂本龍馬伝
- 平均視聴率18.7%
- 岩崎弥太郎の視点から描かれた
『八重の桜』(2013年)
- 綾瀬はるか主演で新島八重の生涯を描く
- 平均視聴率14.6%
- 会津戦争と維新後の日本を描いた
『花燃ゆ』(2015年)
- 井上真央主演で吉田松陰の妹・杉文が主人公
- 平均視聴率12.0%
- 長州藩の女性たちの視点から描いた作品
『西郷どん』(2018年)
- 鈴木亮平主演の西郷隆盛物語
- 平均視聴率12.7%
- 「愛に溢れたリーダー」として描かれた西郷像
『青天を衝け』(2021年)
- 吉沢亮主演で渋沢栄一の生涯を描く
- 平均視聴率14.1%
- 幕末から明治、大正、昭和初期まで描いた長大な作品
高視聴率を記録した幕末時代の名場面
大河ドラマ史上最高の視聴率を記録したのは『赤穂浪士』の討ち入りの回で53.0%でしたが、幕末時代を描いた作品でも高い視聴率を記録した名場面があります。
『篤姫』はシリーズ平均視聴率が24.5%と幕末大河史上最高を記録し、特に江戸城無血開城に向けた篤姫の奔走や、薩摩との別れの場面が多くの視聴者の心に残りました。
『龍馬伝』では、薩長同盟締結の場面や龍馬暗殺のシーンが印象に残っている視聴者が多いでしょう。
特に暗殺シーンは選挙速報のテロップと被り、本来得られるはずの感動を台無しにされたという意味で、記憶に強く残っていそうです……。
『新選組!』の池田屋事件のシーンや、『八重の桜』の会津戦争での籠城戦なども、歴史的瞬間を迫力ある映像で描き出し、高い評価を得ました。
2027年放送予定の『逆賊の幕臣』は、どんな名場面を生み出してくれるのか、期待大です!
大河ドラマの主人公によくある質問
最後に、大河ドラマの主人公によくある質問を回答していきます!
幕末を描いた大河ドラマで最も視聴率が高かった作品は?
歴代の幕末大河ドラマで最高視聴率を記録したのは、1963年の『花の生涯』で32.3%です。
初めての大河ドラマ作品であり、テレビが娯楽として頂点に君臨していた時代だからこその数字かもしれません。
ただし、平均視聴率は2000年代に入ってからの作品がトップに君臨しています。
その作品が2008年放送の『篤姫』(宮﨑あおい主演)で、平均視聴率24.5%を記録。
これは幕末の時代を除いても、2000年以降での最高記録を維持しています(おそらく破られないのではないか)。
新選組が主役の大河ドラマはある?
2004年放送の『新選組!』(香取慎吾主演)が、新選組を主役とした唯一の大河ドラマです。
三谷幸喜が脚本を手がけ、近藤勇を中心に土方歳三や沖田総司など新選組隊士たちの青春群像劇として描かれました。
なお、新選組は他の幕末大河ドラマ(『龍馬伝』『八重の桜』『西郷どん』など)にも度々登場しています。
女性が主人公の幕末大河ドラマはある?
いくつか存在し、代表的なものは以下の3作品です。
- 『篤姫』(2008年) - 宮﨑あおい演じる天璋院篤姫
- 『八重の桜』(2013年) - 綾瀬はるか演じる新島八重
- 『花燃ゆ』(2015年) - 井上真央演じる杉文(吉田松陰の妹)
また、三田佳子・藤村志保・栗原小巻の3人がトリプル主演を務めた『三姉妹』(1967年)も、女性主人公の作品です。
架空の人物が主人公の幕末大河ドラマはある?
古い作品には存在し、以下の2作品が該当します。
- 『三姉妹』(1967年) - 永井家の三姉妹(むら・るい・雪)
- 『獅子の時代』(1980年) - 会津藩士の平沼銑次と薩摩藩士の苅谷嘉顕
特に『獅子の時代』は、菅原文太と加藤剛がW主演で、実在の人物ではない主人公を通じて幕末を描いた異色作です。
坂本龍馬が主人公の大河ドラマは何回ある?
坂本龍馬を主人公とした大河ドラマは2回あります。
- 『竜馬がゆく』(1968年) - 北大路欣也が龍馬を演じた
- 『龍馬伝』(2010年) - 福山雅治が龍馬を演じた
薩長同盟と大政奉還の立役者である坂本龍馬は、主役以外でも登場しているケースは多いです。
今後予定されている幕末大河ドラマはある?
2027年に放送予定の大河ドラマ『逆賊の幕臣』は、まさに幕末をテーマとした作品です。
主人公は幕臣の小栗忠順(おぐり ただまさ)で、松坂桃李が演じます。
幕末といえば、討幕側の観点から描かれることが多いですが、幕府側の視点から幕末を描く作品として注目されています。
まとめ
今回は、NHK大河ドラマの主人公として取り上げてほしい偉人を幕末に限定し、10人紹介しました。
ランキングを振り返ると、維新の志士だけでなく、思想家・教育者・幕臣・女性と、多様な顔ぶれになりました。
伊藤博文のような明治の立役者、佐久間象山のような思想家、千葉さな子のような女剣士など、それぞれが独自の魅力にあふれています。
幕末という激動の時代は、さまざまな立場の人々がそれぞれの信念を持って生きた時代。
だからこそ、多角的な視点で見れば、より深い理解が得られるのではないでしょうか。
現在放送中の2025年大河『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』に続き、2026年は『豊臣兄弟!』(仲野太賀主演)、2027年は『逆賊の幕臣』(松坂桃李主演)が決定しています。
2028年以降の大河ドラマでも、まだ見ぬ魅力的な幕末の偉人たちが主人公となり、新たな視点で描かれることを期待したい!
では今回はこの辺で。
ここまで読んでいただきありがとうございました!