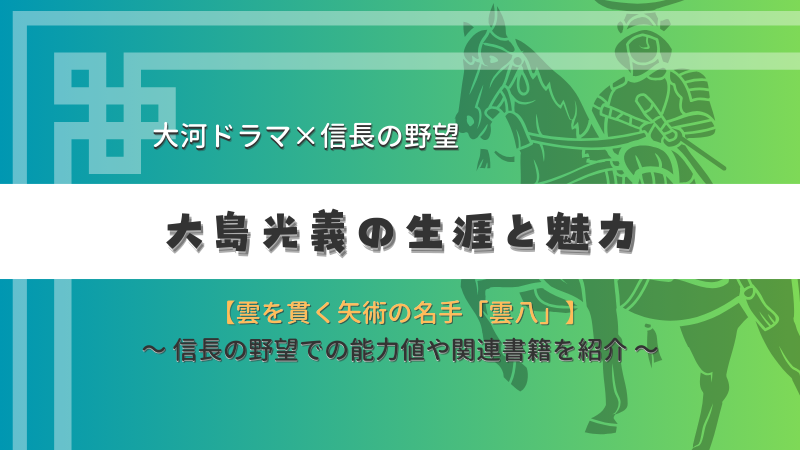
大島光義は、弓の名手として知られ、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑すべてに仕えた戦国武将です。
60歳を過ぎてからも第一線で戦い続け、93歳で関ヶ原の戦いに参陣したことでも有名です。
彼が治めた地では知る人ぞ知る有名人な一方、全国的にみると知名度は低いのが残念なところ。
本記事では、大河ドラマやゲームの「信長の野望」シリーズの話も交えながら、大島光義の生涯や最新情報を解説します。
- 大島光義の出自・功績・逸話
- 信長の野望シリーズでの大島光義
- 小説・映画・書籍に見る大島光義
- 大河ドラマでの大島光義
- ゆかりの地:大島光義と歴史を感じる場所
- 大島光義に関する最新の注目ニュース
- 大島光義の生涯と功績まとめ
大島光義の出自・功績・逸話
大島光義は、美濃国出身の武将で、弓の技量を活かして数々の戦場を駆け抜けた人物です。
| 名前(読み方) |
大島 光義(おおしま みつよし) |
|---|---|
| 別名/渾名/二つ名 | 甚六、鵜八、雲八 |
| 生年 | 永正5年1月7日(1508年2月7日) |
| 没年 |
慶長9年8月23日(1604年9月16日) |
| 父 | 大島 光宗 |
| 母 | おおがみ殿(土岐 政房の娘) |
| 兄弟姉妹 | 不詳 |
| 妻 |
武市 通春の娘 |
| 子 | 光成、光政、光俊、光朝、その他 |
以降では、大島光義の生涯や功績を詳しく見ていきましょう。
出自
清和源氏の流れを汲む新田氏の末裔とされますが、近年の研究では土岐氏流大島氏の末裔という説が有力です。
幼少期に父・光宗を山県合戦で失い、親族の大杉弾正に育てられました。
家の再興を志し、幼い頃から弓術の修練に打ち込んだことで、後の武功の礎が築かれたといいます。
家族や親類
妻は武市通春の娘を迎え、多くの子に恵まれました。
特筆すべきは、関ヶ原の戦いで東軍に属した長男・光成、四男・光朝と、西軍に与した次男・光政、三男・光俊という、東西に分かれて戦った子どもたちの存在です。
この時代ならではの家族の在り方を示す一例といえるのではないでしょうか。
内政や合戦での功績
13歳での初陣から、93歳で臨んだ関ヶ原の戦いまで、実に53回の合戦に参加しています。
その間に受けた感状は41通。
卓越した弓術を武器に、これだけ多くの感状を得られたのでしょう。
特に注目すべきは、永禄7年(1564年)、60歳を超えてから織田信長に召し抱えられ、弓足軽頭として活躍したこと。
坂本の戦いでの働きにより「雲八(うんぱち)」の名を織田信長から賜っています。
雲を貫く矢術の名手という意味を込め、「雲八(うんぱち)」と名付けられたのです。
長篠の戦いでは鉄砲隊と互角の戦果を上げるなど、鉄砲が注目される時代になっても弓の有用性を示し続けました。
さらに、84歳にして法観寺八坂の塔の窓に矢を射込む妙技を披露するなど、老いてなお衰えることのない技量は、周囲の畏敬の的となりました。
晩年と最期
慶長5年(1600年)、93歳という高齢にもかかわらず関ヶ原の戦いに参戦。
大島氏は東西に別れて参戦したものの、大島勢全体としては東軍で武功を上げたため、西軍に参加した子どもたちの罪は許されました。
むしろ家康は大島家に対して厚い信頼を寄せ、真壺・大鷲を与えたばかりか、美濃国の加治田村・絹丸村・川辺村・武儀郡・大迫間村、さらに摂津国の伏見内の地をくわえ、1万8,000石に加増という大盤振る舞い。
この時、豊後国臼杵城主への推挙もありましたが、光義はこれを辞退。
その代わり、南部利直が家康に献じた鷹二羽を拝領し、公儀の鷹場の利用も許されるなど、特別な待遇を受けました。
関ヶ原の翌年には、堀尾可晴、猪子一時、船越景直らと共に家康に召し出され、昔話に花を咲かせたと伝わります。
慶長9年(1604年)、97歳で生涯を閉じるまで、弓の修練を怠ることはなかったそうです。
そのストイックな生き方は、長寿が当たり前になった今でも見習いたいところ!
押さえておきたいエピソード
大島光義にまつわる逸話は、以下を押えておくといいでしょう。
- 樹木射貫きの逸話:樹の陰に隠れた敵を、木ごと射抜いて仕留めた
- 朋輩から「弓は遠間でしか戦えない」と侮られた際、還暦を過ぎてから槍の修行を始め、3年で4通の感状を得た
- 84歳にして法観寺八坂の塔の窓に10本の矢を射込んだ(やらせたのは豊臣秀次)
- 93歳で関ヶ原の戦いに参戦(東軍)
ほかにもエピソードをご存じの人がいたら、ぜひ教えてください!
信長の野望シリーズでの大島光義
戦国時代を舞台にしたシミュレーションゲーム「信長の野望」シリーズで、大島光義は一度も登場したことがありません。
そこで、現在の最新作「信長の野望・新生」で新規武将として登録する場合のステータスを、勝手に設定してみました!
登録する際の参考にどうぞ!
能力値

「信長の野望・新生」での能力値は、以下のように設定してみました。
| タイトル | 政治 | 知略 | 武勇 | 統率 |
|---|---|---|---|---|
| 信長の野望・新生 | 38 | 47 | 93 | 53 |
また、所持戦法や特性は以下のとおりです。
| タイトル | 戦法 | 特性・個性 | 志 | 奉行特性 |
|---|---|---|---|---|
| 信長の野望・新生 | 急襲 |
|
- |
武士心得 |
内政面での功績が不明なので、武勇特化型にしてみました!
ただし、「信長の野望・新生」は弓に特化した戦法や特性が限られているので、雲八らしさを最大限に引き出せないのが残念です。
戦法は「急襲」を設定しましたが、本来であれば、弓寄りのものや固有戦法を設定してあげたいところです。
奉行特性も迷いに迷って、武士心得に。
その代わり、特性には「射手」を設定したので、高台付近にいる敵を特技の弓で蹴散らしてくれるでしょう!
みなさんなら、大島光義のステータスはどのように設定しますか?
コメントなどで教えていただけるとうれしいです!
ゲーム内で向いている役割
紹介したステータスは、戦闘かつ副将タイプ。
戦闘能力が低めの部隊長のステータスを底上げする役割が向いています。
統率を低めに設定しているので、部隊長にするには防御が物足りないですが、火力重視で敵をいなす前線部隊の長として活躍させるのもありといえばあり!
部隊の被害は大きいかもしれないけど、武勇93なので相手にもまた大打撃を与えられます。
また、部隊長にした場合は高台の射撃できる場所を積極的に押さえれば、戦局を優位に進められるでしょう。
大島雲八を中心に天下統一の覇業を成し遂げましょう!
大島光義プレイにおすすめのタイトル
今回ステータスを設定したのは「信長の野望・新生」でしたが、ほかのタイトルでも新規武将として登録すれば、大島光義プレイが可能です!
おすすめの「信長の野望」シリーズは、以下4つのタイトルです。
それぞれでおすすめポイントが異なるので、プレイスタイルに合うものを選びましょう!
| タイトル | おすすめポイント |
|---|---|
| 信長の野望・創造PK |
|
| 信長の野望・創造 戦国立志伝 |
|
| 信長の野望・大志 |
|
| 信長の野望・新生 |
|
「信長の野望・創造 戦国立志伝」以外のタイトルの場合、大名プレイをするには以下どちらの方法が必要な点に注意してください。
個人的には、「信長の野望・創造 戦国立志伝」での武将プレイがおすすめ!
小説・映画・書籍に見る大島光義
大島光義を主人公とする小説は1冊あります。
新潮文庫の『九十三歳の関ヶ原: 弓大将大島光義』(近衛龍春著)という作品です。
織田信長が桶狭間の戦いで海道一の弓取り・今川義元を倒したあと、つまり、大島光義はまだ美濃の斎藤氏に属していたころから話は始まり、関ヶ原の戦いを経て亡くなるまで、その生涯が丁寧に紡がれています。
知る限りではこの小説以外ない認識ですが、ほかに大島光義の関連書籍をご存じの方がいたら、ぜひ教えていただきたく!
大河ドラマでの大島光義
NHK大河ドラマで大島光義が登場した作品は、現時点ではありません。
しかし、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』は登場する可能性があります。
大島光義は、本能寺の変後に丹羽長秀に仕え、そののち羽柴秀吉の足軽大将として6,000石を領しています。
さらにそののち、秀吉の甥である秀次付きとなっているのです。
前述の京都法観寺八坂の塔の窓に矢を射った逸話は、秀次の命によるもの。
豊臣秀次といえば、『豊臣兄弟!』の主人公・豊臣秀長と関係の深い人物です。
可能性はゼロに近いかもしれませんが、初登場に期待を寄せたいところです!
ゆかりの地:大島光義と歴史を感じる場所
大島光義のゆかりの地を2つ紹介します。
妙興山 大雲寺(岐阜県関市)
大雲寺は、岐阜県関市伊勢町の安桜山東南麓にある日蓮宗の寺院で、山号は妙興山。
慶長6年(1601年)、大島光義が元家臣で日蓮宗の僧侶となった真如山日昌(俗名矢島定昌)を開山として建立しました。
当初は妙興庵という小庵でしたが、後に現在地に移転し、現在の山号寺号となったそうです。
寺宝として大島光義の肖像画や所用の甲冑、書状など貴重な遺品を所蔵しています。
光義から六代目の大島四朗義苗と七代目の大島雲四朗義順が愛用した甲冑具足(鎧、兜)は岐阜県関市の文化財に指定され、江戸時代初期の名匠・早乙女家忠の作として知られています。
境内には、大島家歴代の墓所が設けられています。
興味深いことに、関市には同名の大雲寺がもう一つ存在します。
下迫間にある白華山 大雲寺(大雲禅寺)は、光義の三男・大島光俊が建立した臨済宗妙心寺派のお寺。
光俊の子孫は江戸時代を通じて旗本として同地を治め、この大雲寺(禅寺)には旗本大島家の墓所や関連遺品が残されています。
それぞれが大島家の歴史を今に伝える貴重な史跡となっているので、近くにお立ち寄りの際はぜひ!
関城跡(岐阜県関市)
安桜山に築かれた関城は、大島光義がかつて仕えた長井道利(長井隼人)が城主を務めた山城です。
織田信長の東美濃侵攻時には、加治田城、堂洞城とともに斎藤方の守りの要として機能しました。
光義もここを拠点に、織田軍との攻防戦を幾度となく経験していたはずです!
現在は安桜山公園として整備され、北側斜面に残る三段の腰曲輪や竪堀など、当時の遺構を見学できます。
山頂の展望台からは関の街並みを一望でき、遠く金華山(岐阜城)まで見渡せます。
大島光義が若き日に弓を携え、この城を守った往時を偲ぶことができる貴重な史跡となっています。
妙興山 大雲寺のすぐそばにあるので、お寺とあわせて訪れてみてください。
関鍛冶伝承館(岐阜県関市)
刀剣の町として知られる関市の歴史と伝統を今に伝える施設です。
1階の刀剣展示室では、「関の孫六」として名高い孫六兼元や和泉守兼定の日本刀をはじめ、戦国期の関で作られた名刀の数々を見ることができます。
大島光義も、これらの関の刀工たちが打ち出した刀を目にし、あるいは使用していたことでしょう。
毎月1回、敷地内の日本刀鍛錬場で「古式日本刀鍛錬」の実演が行われるので、これにあわせて訪れるとより楽しめます!
大槌と小槌で鋼を打ち延ばす際の小気味良い音。
立ち昇る鉄の匂いや飛び散る火花など、大島光義が生きた戦国時代さながらの光景を感じ取れます。
関鍛冶伝承館も、大雲寺や関城跡と併せて訪れやすい場所にあるの、大島光義ゆかりの地を巡る際のスポットの1つに加えてみてください。
大島光義に関する最新の注目ニュース
現時点では、大島光義に関する最新の史料発見などの大きなニュースは見あたりませんでした。
今後ニュースを発見次第、更新していく予定です!
大島光義の生涯と功績まとめ
大島光義は、弓に生涯を捧げた戦国武将といっても過言ではありません。
13歳での初陣から93歳での関ヶ原出陣まで、一度も弓を手放すことなく戦い続けた武将の生き様は、長寿時代となった今こそ参考にしたい!
しかし、ゆかりの地である関市(岐阜県)では有名でも、一般的にはマイナー武将の1人。
戦国時代が好きな人でもなければ、なかなか知る機会はないでしょう。
戦国時代を知るきっかけとなるゲーム「信長の野望」シリーズにも、残念ながら登場したことがありません。
今後の新作で弓大将・大島光義(雲八)の登場を心待ちにしています(コーエーテクモさん!)。
そして本記事をきっかけに、大島光義に興味を持ってもらえたらうれしいです!
では今回はこの辺で。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
©コーエーテクモゲームス